松本での稽古を一旦抜け、東京からの同僚、ソリスト、バルセロナ交響楽団と合流して8/1に広島でベートーベンの交響曲《第九》を演奏した。7月にも同じ演目で演奏したが、2回目ということもあって、とは説明できないほど全く別の、違う世界への扉を皆で開いたような感覚のする演奏になった。あの時よりも良いとか悪いとか、演奏はそうであるものではないのだからもっとうまく説明したいのだけど。
この日は夕方からのリハーサルだったので、それまでの時間に広島平和記念資料館へ行く。改修工事と展示整備で2年間ぶりに開館された本館を含めゆっくりと時間をかけて回ることができた。すぐそばにある広場では、8月6日の、原爆が広島に落とされた日にある平和記念式典の準備が着々と進められており、白いテントが緑の芝生に作るくっきりとした陰を作っていた。

広島の宿泊先の部屋のドアーに掛けてくれた新聞は中国新聞だった。恥ずかしい話、すっかり新聞を読む習慣を無くしているが、こういう時は読んでおいても良いだろうと起きたままの布団の上で紙面を開いた。8月になったばかりの日だ。
その中の記事をひとつとっておいたので載せておく。ひろしま美術館での《かこさとし展》についても興味深く読んだが、冒頭部分が最後まで尾を引いた
“そんな夏だからこそ、戦争回避へ何をすべきか、しっかり考えたい。8月ジャーナリズムと揶揄されようとも。”
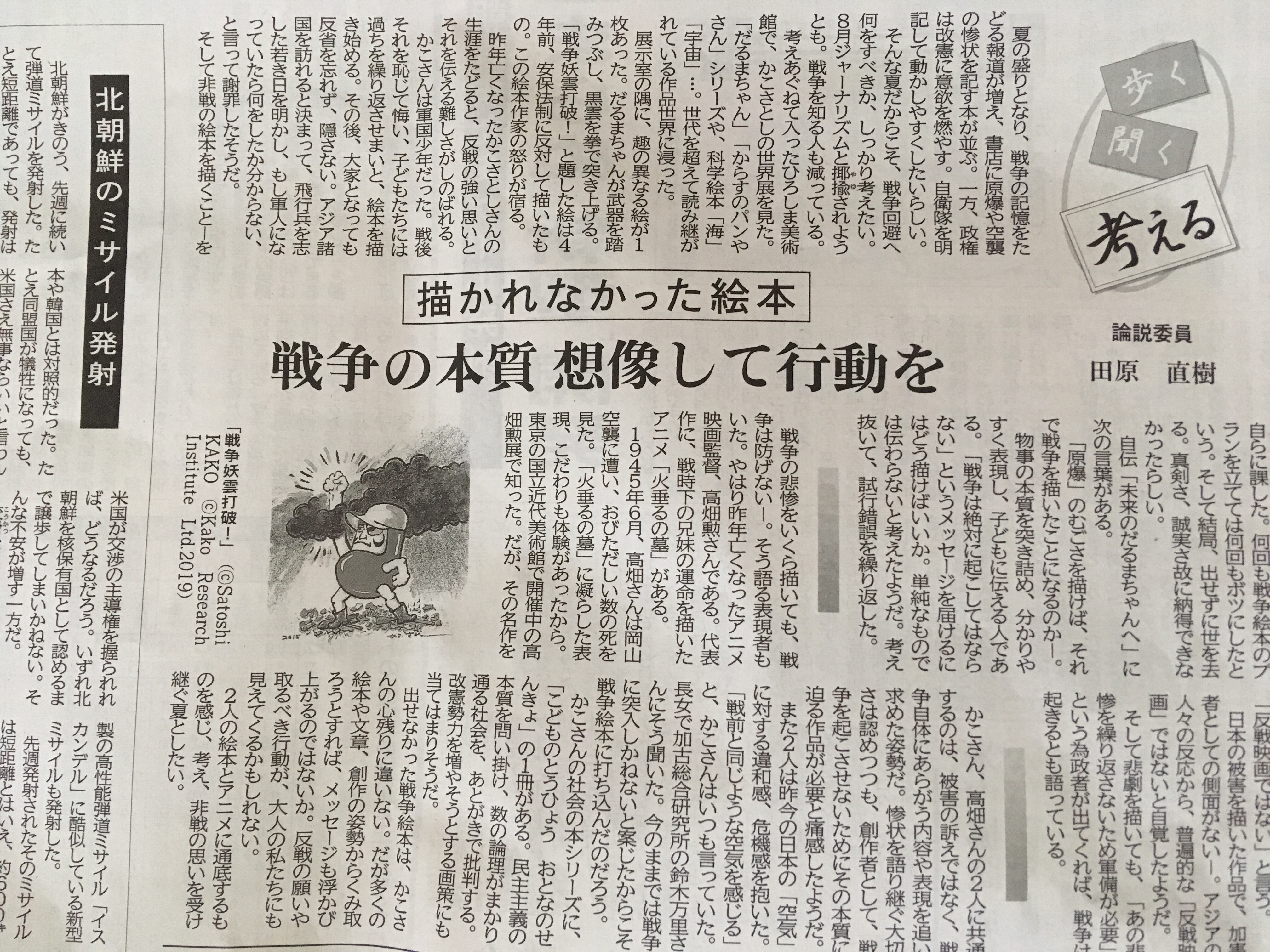
戦争の足音がする、と言われて何年経つだろう。それは戦争を経験した世代が、当時体験した世相の変化というものを今の時代に感じていたからだろう。かの惨劇への第一歩はあの時である、とは誰も言えない。物事は常に連続していて、映画のフィルムのコマが落ちては成り立たない、と例えて良いのだろうか。その連続したコマに、私がいた、のを後になって私が見つけた時になんと思うのだろう。そう考えるとただ恐ろしくて震える。
しっかりと立っていようと思う。
手を繋ぐことができるほどの場所にいる人に優しさと愛の言葉を持って。
