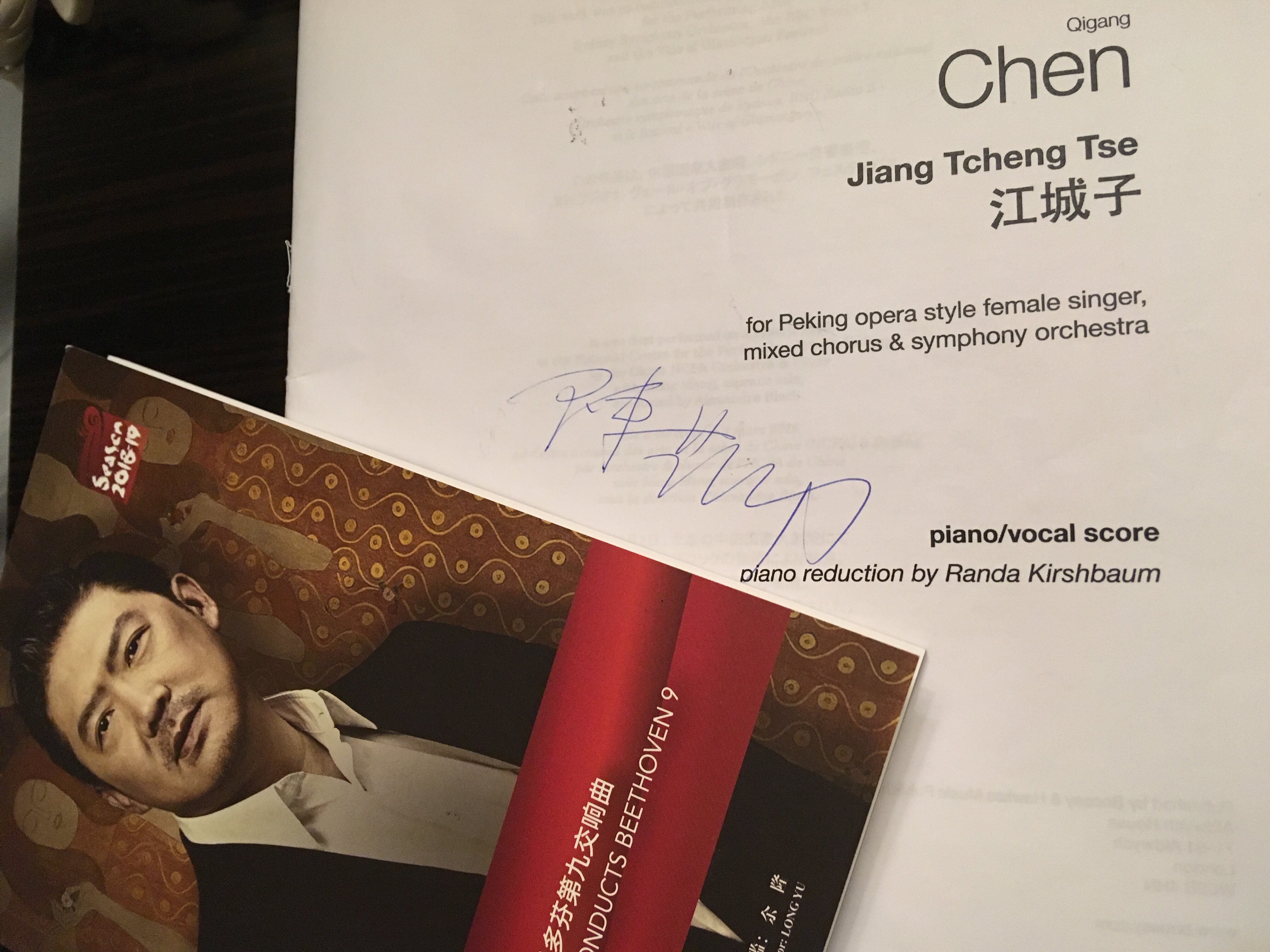《オランダ人》で舞台に立っていたブリン・ターフェルBryn Terfelやペーター・ザイフェルトPeter Seiffertの雄姿を見られる機会などそうあることではないから、ホールでのリハーサルや本番で自分の出番がない時は舞台袖まで行って、舞台裏まで響くその声だけを聴きに行ったり、袖口から見える横顔だけでもと隙間から覗く様に見たりしていた。
コンサートの1時間前にはまだ楽屋口でサインに応じていた彼らは、一歩舞台に出て、または一言歌い出すその瞬間には、もう自分の役柄としてそこで立っていて、僕たちもそうやって舞台にいるつもりでも、さっき楽屋から舞台までの間に「ウェールズ最高!」と言っていた人との差はとんでもない。もちろんザイフェルトがエリクErik役を何百回やっていることを知っていても、目の前では、2幕の登場や、3幕のバラードは常に新しく、作り込まれていない新鮮な言葉を歌っている様に感じられる。言葉の使い方が正しいかどうかわからないが、そのままである、という意味でオランダ人然として、エリク然としていた。
然(ゼン)という言葉は「しかり。そのとおり。そのまま。」「状態を表す語を作る助字」と辞書にはあり、形容詞に付けたり、付けることでその後を形容させる。音楽家は、いわゆるクラシックにおいては楽譜の再現、表現が果てしない目標なのであるが、その◯◯然でとなるのは、舞台の成功以上の価値の高いものだと僕は思っている。
オペラや歌曲ならば、書かれている言語に支配されるのであろうが、必ずしも母国語だから、とか流暢に話せるからとかでその自然な、まるで景色のようにいることが成立することはないということは知っている。外国人だから、とか有名人だからそうであるわけでも無い。(もちろんそれは個人的な好き嫌いということを完全では無いけれど除いて)
何百回と演じながらもその一瞬をどれだけ役に、その音楽に向き合ったかという結果、と随分簡単に言ってしまうが、そんな音楽家として純粋な事なんだろうな。漠然とした所にしか僕の考えは至らないが、◯◯然とする、いや、なるのか、の方が「人」としても自然でいられると思わせてくれる、温かい人間性を彼らは持っている。そうありたいと思わせてくれるし、そんな所に果てしない憧れを持つ。