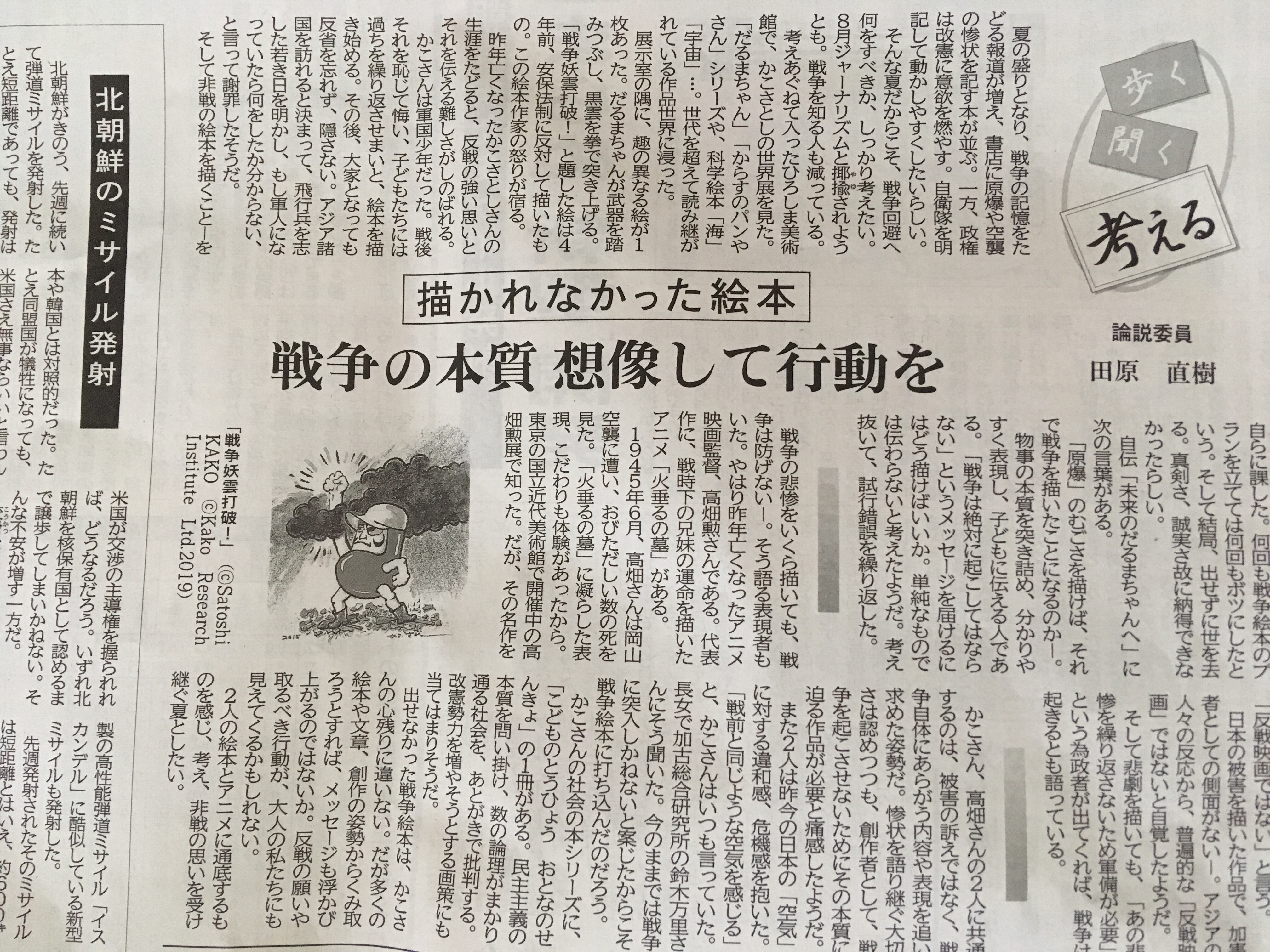ヘルベルト・ブロムシュテット指揮によるモーツァルトが作曲したミサ曲ハ短調(K.427)をNHK交響楽団の演奏と共に終えた。(11月22,23日)マエストロが92歳、というのはこの演奏会には何の飾りにもならないが、自身の演奏活動と共にN響との40年近くにもなる長く、強い信頼関係は音楽の姿としてあった。
僕は2016年の同楽団によるベートーベンの”第九”で合唱として初めマエストロ・ブロムシュテットと演奏した。合唱の音楽稽古から、音楽に身を捧げる姿を目の前にし、作曲家、楽曲を間において僕達と絶えない会話をする様は今回も何も変わることはなかった。
10月10日に演奏した、トン・コープマン指揮による、同じくN響とのモーツァルトのレクイエムの経験がどこか繋がりを持つ。2つとも作曲家が完成し得なかった、神に捧げる曲としての音楽。
普段、いわゆる音楽におけるロマン派以降の楽曲を歌うことが多い者にとってはやや特殊なアーティキレーション(これは何と訳せば良いのか)をマエストロ・コープマンとの音楽で表現した。長い旋律線にかかる、強調された強弱、弦楽器が短く弓を当てるような息の使い方、ヴィブラートを抑えてハーモニーをより強く意識する事で得られる内省。個々人の技術によって、それらは音にする事が出来るが、指揮者からは表現にあたり「あなた方の心に触れてください」と言われた。その言葉は、頬に柔らかく風が触れる様に感じた。演奏する事は僕の生活の主たる事であるけれど、もっと根源たる、当前の様で、気づくとなんとも言えない幸せな思いがした。
今回のマエストロ・ブロムシュテット からは、歌手もオーケストラもテキストに集中するように促された。同じフレーズを繰り返しリハーサルし、時にはオーケストラだけ、時には合唱だけ(アカペラで)演奏し、お互いのひとつの音楽に向けた着地を探しながら、まるで学生の頃の音楽の共有に近い感覚を持った。その手法ではなく、僕の中に起こった感覚でしかいのだけれど。2月にリッカルド・ムーティ 指揮のシカゴ響とのヴェルディのレクイエムでも同じ感覚があった。もちろん聴衆と我々の間に音楽はあるのだけれど、ごく私的な空間に没入すると言うのだろうか、未だにうまく表現できずにいる。
モーツァルトのレクイエムは12月に、ミサ曲ハ短調は2月にTV放映があるそうなので、またこちらでお知らせできたらと思う。